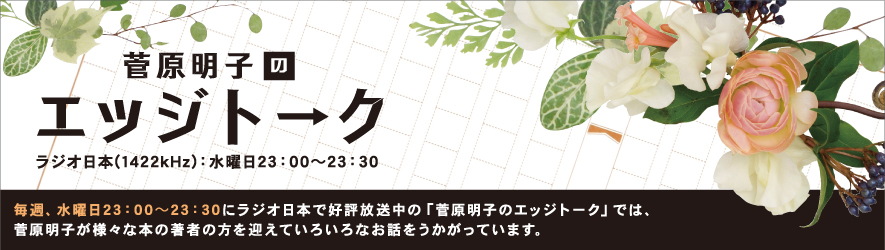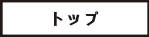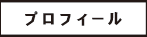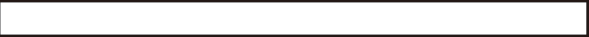木山啓子
特定非営利活動法人ジェン(JEN)理事・事務局長。大学卒業後、電機メーカーなどに約7年間勤務。その後ニューヨーク州立大学大学院(社会学)修士課程修了。1994年AMDAネパール勤務を経てJEN創設に参加し、旧ユーゴスラビア現地統括責任者として6年間駐在。2000年から現職。以降、モンゴル雪害、アフガニスタン内戦、インド西部地震、エリトリア帰還難民、イラク復興、新潟県中越地震、パキスタン地震、スマトラ沖地震、レバノン難民、中越沖地震、南部スーダン帰還難民、ミャンマー・サイクロン災害、ハイチ地震などの支援活動に従事、指揮する。 一方で「自立支援とは?」や「難民・被災者の教え」「極限の中で人は何を求めるのか」「学び方・働き方」などをテーマに、全国各地で講演活動を展開、多忙の日々を送っている。2005年エイボン女性功績賞受賞、日経ウーマン誌ウーマン・オブ・ザ・イヤー2006大賞受賞。