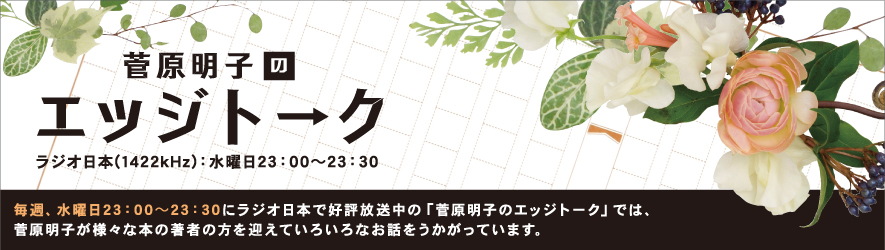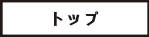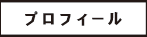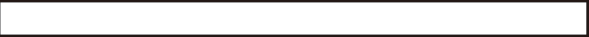|
||||
桑原晃弥
1956年、広島県生まれ。慶應義塾大学卒。業界紙記者、不動産会社、採用コンサルタント会社を経て独立。転職者、新卒者の採用と定着に関する業務で実績を残す。また、トヨタ式の実践、普及で有名なカルマン株式会社の顧問として「人を真ん中においたモノづくり」に関する書籍やテキスト、映像の企画、執筆、編集を行っている。 著書に『スティーブ・ジョブズ名語録』『「ものづくり現場」の名語録』(以上、PHP文庫)『1分間スティーブ・ジョブズ』(ソフトバンククリエイティブ)『ジョブズはなぜ、「石ころ」から成功者になれたのか?』(経済界)などがある。